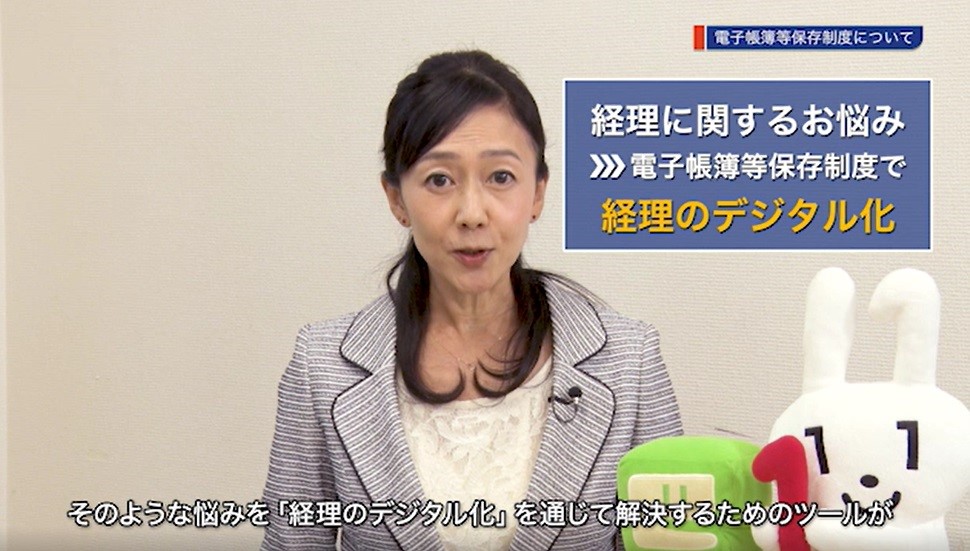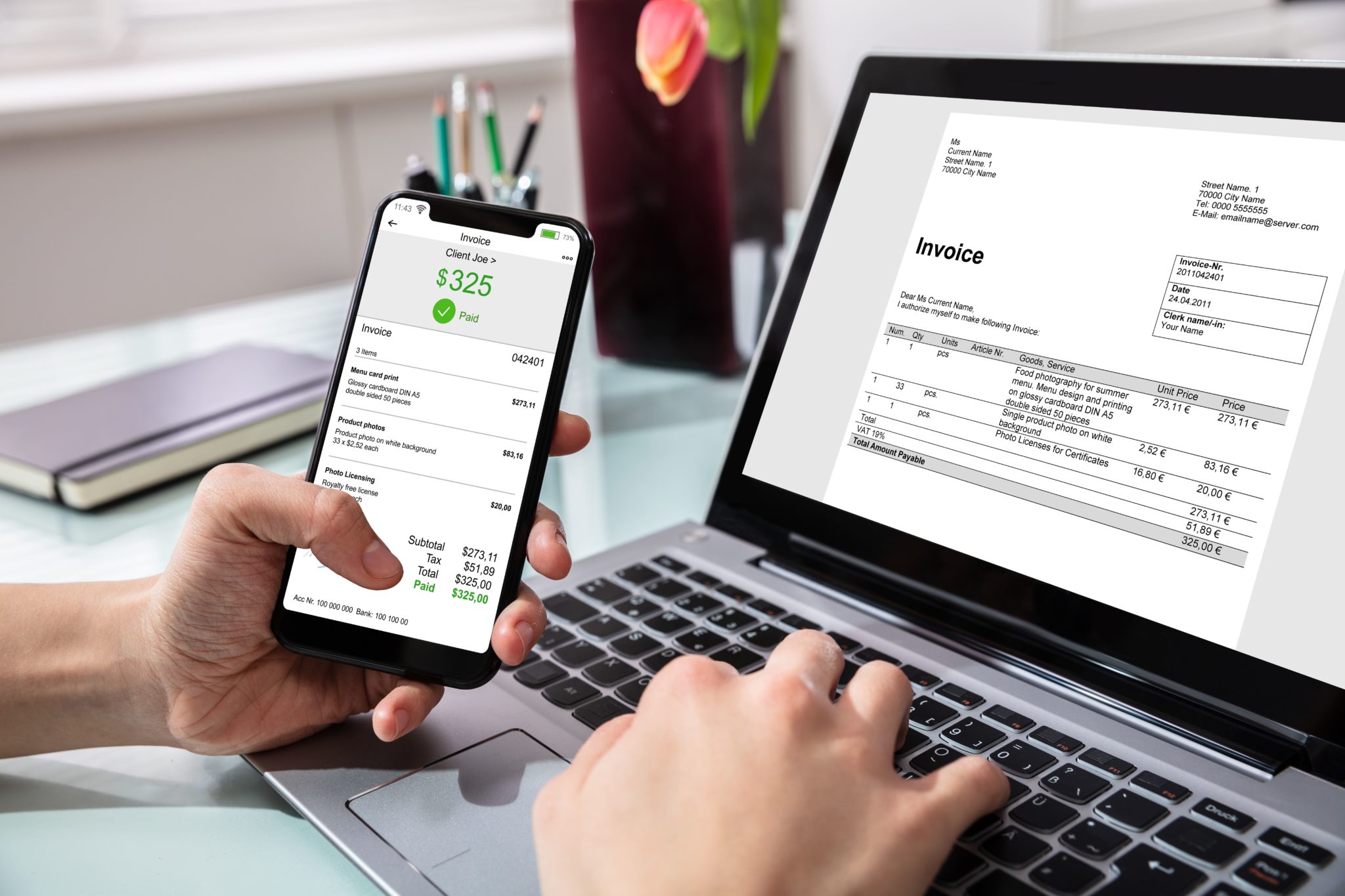1.電子帳簿保存法への対応義務
電子帳簿保存法とは、正式には「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」と言い、本来は「紙」で保存することが原則である国税関係帳簿や国税関係書類を、文書保存の負担の軽減を図る観点から、電子データで保存することを特例として認める法律です。
この法律自体は1998年から施行され、電磁的記録(電子データ)による保存要件等も改正を繰り返し、現状では、令和3年度の改正により令和4年1月から施行されている改正電子帳簿保存法が最新となります。
電子帳簿保存法では主に以下の2点が定められています。
(1)各税法で原則、紙(書面)で保存が義務づけられている帳簿書類について、一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること
(2)電子的に授受した取引情報の保存義務等
この(1)は、下図の「区分①:電子帳簿等保存」と「区分②:スキャナ保存」が該当し、「電子保存を利用したい事業者向けの制度」(任意)です。
(2)は、「区分③:電子取引」が該当します。電子取引は「電子取引は電子帳簿保存法上の要件を満たしたデータ保存が義務付けられた制度」(義務)となります。

出典:国税庁 電子帳簿保存法が改正されました(R3.12改訂)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021012-095_03.pdf
この任意と義務の関係は、別の国税庁の資料では下記のように表現されています。
・任意:利用したい方が利用する制度
・義務:ご対応いただく必要がある制度

出典:国税庁 令和3年度改正電子帳簿保存法 YouTube動画「国税庁動画チャンネル」(令和4年1月更新)掲載資料
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0022001-105.pdf
2.電子帳簿保存法の改正事項
電子帳簿保存法は、今回の改正で保存要件等が大幅に緩和され、全ての区分(電子帳簿保存、スキャナ保存、電子取引)で改正事項が発生しています。以下に改正事項を一覧化した概要を示します。なお特に留意すべき点は背景色をつけています。
| 電子帳簿保存法の改正事項(まとめ) | |||
| 電子帳簿保存 | 1. | 税務署長の事前承認制度が廃止されました。 | |
| 2. | 優良な電子帳簿への過少申告加算税に係る軽減措置が整備されました。 | ||
| 3. | 最低限の要件を満たす電子帳簿(その他の帳簿)についても、電磁的記録による保存等が可能となりました。 | ||
| スキャナ保存 | 1. | 税務署長への事前承認制度が廃止されました。 | |
| 2. | タイムスタンプ要件、検索要件等について、次のとおり要件が緩和されました。 | ||
| (1) | タイムスタンプの付与期間を、最長約2か月と概ね7営業日以内に緩和されました。 | ||
| (2) | 受領者等がスキャナで読み取る際の国税関係書類への自署は不要となりました | ||
| (3) | 電磁的記録について訂正又は削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認することができるクラウド等*で、入力期間内にその電磁的記録の保存を行ったことを確認することができるときは、タイムスタンプの付与は不要となりました。 *訂正又は削除を行うことができないクラウド等を含む | ||
| (4) | 検索要件の記録項目について、取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先に限定されるとともに、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じる場合には、範囲指定及び項目を組み合わせて条件を設定できる機能の確保は不要となりました(可視性の検索要件②及び③に相当する要件) | ||
| 3. | 適正事務処理要件*が廃止されました。 *相互牽制、定期的な検査及び再発防止策の社内規程整備等 | ||
| 4. | スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置が整備されました。 | ||
| 電子取引 | 1. | タイムスタンプ要件及び検索要件について次のとおり要件が緩和されました。 | |
| タイムスタンプ要件に係るタイムスタンプの付与期間及び検索要件に係る検索項目について「スキャナ保存(区分②)に関する改正事項」の2(1)と(4)と同趣旨の改正が行われたほか、 基準期間(注)の売上高が1,000 万円以下である方(小規模な事業者)について、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索要件の全てが不要とされました。 | |||
| 基準期間*の売上高が1,000 万円以下である方(小規模な事業者)について、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索要件の全てが不要となりました。 *「基準期間」とは、個人事業者については電子取引が行われた日の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの期間をいい、法人については電子取引が行われた日の属する事業年度の前々事業年度をいいます。 | |||
| 2. | 適正な保存を担保する措置として、次の見直しが行われました。 | ||
| (1) | 申告所得税及び法人税*における電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、その電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置は、廃止されました。 *消費税における電子取引の取引情報等に係る電磁的記録については、引き続き出力書面による保存が可能です。 | ||
| ※令和5年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えありません(事前申請等は不要)。令和6年1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いします。 | |||
| (2) | 電子取引の取引情報に係る電磁的記録に関して、隠蔽し、又は仮装された事実があった場合には、その事実に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税が10%加重される措置が整備されました | ||
出典:国税庁 電子帳簿保存法が改正されました(R3.12改訂)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021012-095_03.pdf
今回の電子帳簿保存法の改正の中でも、特に影響が大きい項目が、電子取引2(1)「電子的に授受した授受した取引情報をデータで保存することの義務化」です。(背景色:緑色)
但し、宥恕措置により令和5年(2023年)12月31日までの電子取引については、データ保存ではなく紙による保存も認められています。(背景色:黄色)
なおこの宥恕措置は、所轄の税務署長が「止むを得ないと判断」した場合に、紙に印刷して保存することを認める措置です。そのため原則として、紙で電子取引データの保存はできないものと考えて、電子化への対応準備を進めるのがよいでしょう。
メールに添付された請求書PDFを紙に印刷して保管する事業者は、現状でも少なくないと思います。こうした状況の中で、今回の改正電帳法で電子取引によるデータ保存が義務化されたことは、電子帳簿保存法の保存要件等を今まで以上に正しく理解する必要性を高めた、と言えます。
3.改正電子帳簿保存法による電子取引データの保存要件
改正された電子帳簿保存法では、「EDI取引」「電子メールによる送付(添付ファイルを含む)」「Webサイトを通じた情報の授受」などの電子取引によって受領した電子取引データについては、当該保存要件が下表のように定められています。
| 改正電帳法における電子取引データの保存要件(電子インボイスで電子取引を行う際の保存要件) *下線部:令和3年度税制改正により変更があった箇所 | |||
| 真実性の要件 | 以下の措置のいずれかを行うこと | ||
| ① | タイムスタンプが付された後、取引情報の授受を行う | ||
| ② | 取引情報の授受後、速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付すとともに、保存を行う者又は監督者に関する情報を確認できるようにしておく | ||
| ③ | 記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認できるシステム又は記録事項の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の授受及び保存を行う | ||
| ④ | 正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定め、その規程に沿った運用を行う | ||
| 可視性の要件 | 保存場所に、電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと | ||
| 電子計算機処理システムの概要書を備え付けること | |||
| 以下の検索機能を確保すること | |||
| ① | 取引年月日、取引金額、取引先により検索できること | ||
| ② | 日付又は金額の範囲指定により検索できること | ||
| ③ | 二つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること | ||
| ※1.ダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、②③は不要 | |||
| ※2.保存義務者が小規模な事業者でダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索機能は不要。 | |||
出典:国税庁 電子帳簿保存法が改正されました(R3.12改訂)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021012-095_03.pdf
電子取引によって受領した電子取引データは、「真実性の要件」と「可視性の要件」を共に満たす必要があるので、例えば「メールで受信した請求書PDF」を「単にPC内のメールソフトで保存しているだけでは、真実性の保存要件を満たさない」ことに注意が必要です。
また可視性の要件を満たすためには、検索機能で、対象となる電子取引データを探せる必要があります。「電子帳簿等保存*」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」のいずれにおいても、以下の①~③の条件を全て満たす形で検索要件を充足することが必要となります。
*優良な電子帳簿の要件を満たさない「その他の電子帳簿」は含みません。
—————————————————————————–
・検索条件①:取引等の「日付・金額・相手方」で検索ができる
・検索条件②:「日付・金額」について範囲を指定して検索ができる
・検索条件③:「日付・金額・相手方」を組み合わせて検索ができる
—————————————————————————–
現実的には、こうした検索機能を満たすためには、会計ソフトベンダなどが提供する電子帳簿保存法対応サービスを利用するか、次項に示す「検索要件を満たす例外対応」を活用する方法があり得ます。
4.電子取引データの検索要件を満たす例外対応
電子取引データの可視性を満たすには、前項の「検索条件①~③」を全て満たすことが求められていますが、例外対応として、以下の3パターンが示されています。
【例外1】
「可視性の要件」に対応するためには、システム機能の利用が欠かせませんが、必ずしも大規模なシステム改修や、ソリューションベンダが提供する電子帳簿保存法対応サービスの適用を必須とするものではありません。
以下のように一定のルールに基づいて電子インボイスを保存・格納することで、検索機能の要件を満たすことも有効な対策です。電子帳簿保存法一問一答では、以下の事例が記載されています。
—————————————————————————————————————-
1. 請求書データ(PDF)のファイル名に、規則性をもって内容を表示する。
例) 2022年(令和4年)10月31日に株式会社国税商事から受領した110,000円の請求書
⇒「20221031_㈱国税商事_110000」
2. 「取引の相手先」や「各月」など任意のフォルダに格納して保存する。
3. 【問28】に記載の規程*を作成し備え付ける。
なお、上記1の代わりに、索引簿を作成し、索引簿を使用して請求書等のデータを検索する方法によることも可能です。受領した請求書等データのファイル名に連番を付して、内容については索引簿で管理する。
—————————————————————————————————————-
*問28の規定:「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程」
出典:国税庁 電子帳簿保存法一問一答(電子取引関係)令和4年6月版・問15
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0022006-083_06.pdf
こうした管理簿を利用した具体的な利用シーンは、国税庁が提供する動画の中でも公開されています。なおこの動画は、最新の改正電子帳簿保存法(令和3年度の税制改正)の内容に基づいて制作されているので、制度全般を把握する際にも参考となります。

出典:国税庁 【経理のデジタル化】はじめませんか、電子帳簿保存・スキャナ保存【令和3年11月配信】
https://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/202111_a/webtaxtv_wb.html
【例外2】
保存データについて、質問検査権に基づいて当局が行う「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしている場合には、条件②③(範囲指定、組み合わせでの検索)は不要です。
ただし、税務職員がダウンロードを求めたデータ全てについて応じられること等が必要となります。
【例外3】
電子取引データ保存については、以下をいずれも満たす場合には、検索要件自体を満たすことが不要となります。
①当局が質問検査権に基づいて行う「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしている
②2年前(2期前)の売上高が1,000万円以下
5.無くならない紙の請求書、レシート等の電子保存要件
電子取引データが普及しても、郵送されてくる紙の請求書や経費精算などで利用する紙のレシート等が、インボイス制度後、全て電子化されるとは考えられません。一方で紙の原本を保存する運用と電子保存を併用すると、ペーパーレス化は進展せず、経理の業務負担も削減できません。
紙(書面)の請求書、領収書、レシート等を、電子帳簿保存法によって電子保存する場合は、スキャナやデジタルカメラ、スマートフォンで撮影・スキャンした画像データを、「スキャナ保存要件」に沿ってデータ保存することが求められます。
このスキャナ保存要件も電子取引の保存要件と同様に、「真実性の要件」と「可視性の要件」を共に満たす必要があります。
ただしスキャナ保存の要件は、紙の請求書、領収書、レシート等の証憑画像を電子化する際に、電子データの改ざんや不正も発生しやすくなるため、電子帳簿保存法の中でも厳格な規定となっています。
詳細は以下の巻末資料を参照してください。
巻末資料1:スキャナ保存要件(令和4年1月以後にスキャナ保存を行う場合の要件)
6.電子インボイスは改正電帳法に準拠した保存が必要
改正電子帳簿保存法は既に2022年1月から施行されていて、宥恕規程があるものの「電子取引は電子帳簿保存法上の要件を満たしたデータ保存が義務付けられた制度」として既に開始されています。
2023年10月1日開始のインボイス制度後は、電子インボイス(電磁的記録による適格請求書等)を提供又は受領した場合は、改正された電子帳簿保存法に準拠した保存が必要となります。
国税庁の電子インボイスに関する資料では、下図のように記載されています。

出典:国税庁 インボイス制度 オンライン説明会 基礎編 参-1インボイス等の電磁的記録による提供
https://drive.google.com/file/d/18pDUuuL4ta_5D7bkaIe3iezOsE16WMve/view?usp=sharing
電子インボイスの請求書PDFは、電子取引データです。そのため電子帳簿保存法における電子取引データの保存要件に沿った保存が必要となります。
具体的には、「改正電帳法における電子取引データの保存要件」の「真実性の要件」に記載したように、例えばタイムスタンプ*を付与する場合は、
①電子インボイスにタイムスタンプを付与してから取引先に送付する
②電子インボイスを取引先に送付した後で、インボイスに速やかに(最長約2か月+概ね7営業日以内)タイムスタンプを付与し、これを控えとして保存する
2パターンがあることが分かります。
*一般財団法人 日本データ通信協会が認定する「時刻認証業務認定事業者」の認定に係る業務により発行されるタイムスタンプを付与する必要があります。
②の方法は、タイムスタンプを付与する期間を「速やかな期間内に」付与したかどうかを管理し、「保存を行う者又は監督者に関する情報を確認できるようにしておく」ことも求められているので、システム対応としてはこれらの対応措置も必要になってきます。
③の方法は、電子インボイスを訂正・削除することが出来ないか、訂正・削除した場合でも履歴が残るクラウドサービス等を使って電子インボイスをやり取りすることを示しています。この場合はタイムスタンプの付与は必要ありません。
④の方法は、電子インボイスの訂正・削除を行わないことを原則とし、仮に訂正・削除を行う場合には、社内で定めた事務処理規程に従って、所定の申請書等の記載と社内承認を経て、訂正・削除を行う運用を行うことになります。
加えて、インボイス制度後は、適格請求書発行事業者には、原則、以下の義務が課されます。
—————————————————————————————————————-
適格請求書発行事業者の義務
(1)適格請求書の交付
取引の相手方(課税事業者)の求めに応じて、適格請求書(又は適格簡易請求書)を交付する
(2)適格返還請求書の交付
返品や値引きなど、売上げに係る対価の返還等を行う場合に、適格返還請求書を交付する
(3)修正した適格請求書の交付
交付した適格請求書(又は適格簡易請求書、適格返還請求書)に誤りがあった場合に、修正した適格請求書
(又は適格簡易請求書、適格返還請求書)を交付する
(4)写しの保存
交付した適格請求書(又は適格簡易請求書、適格返還請求書)の写しを保存する
—————————————————————————————————————-
出典:国税庁 インボイス制度 オンライン説明会 基礎編P.9
https://drive.google.com/file/d/18pDUuuL4ta_5D7bkaIe3iezOsE16WMve/view?usp=sharing
適格請求書発行事業者は、基本的に適格請求書(インボイス)の交付と受領の両方の立場となり、提供した電子インボイスと受領した電子インボイスは、共に電子帳簿保存法に準じた保存が7年間必要になります。更に紙で受け取った適格請求書等(インボイス)を電子保存する場合も、同様に改正電子帳簿保存法(改正電帳法)の保存要件に準ずる形で保存する必要があります。
7.電子帳簿保存法の電子取引データとインボイス制度の電子インボイス
インボイス制度は、消費税法に係る制度です。消費税法では、電子インボイスであっても、整然とした形式及び明瞭な状態で出力した紙(書面)による保存も、認められています。
一方、申告所得税または法人税の納税者に係る電子帳簿保存法では、電子取引による請求書・領収書・納品書等を紙(書面)で保存することは認められなくなりました。
国税庁の電子帳簿保存法に関する資料では下図のように記載されています。

図出典:国税庁 電子帳簿保存法が改正されました(R3.12改訂)下線は筆者追記。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021012-095_03.pdf
このような法制度の関係から、電子インボイスを仮に紙(書面)で保存した場合には、消費税法上の仕入税額控除は受けられますが、申告所得税法または法人税法においては、「適切に保存された証憑がない状態」となってしまいます。
したがって多くの事業者が、法人税・所得税の納税者であることを鑑みれば、結果的に電子インボイスは、改正された電子帳簿保存法で義務化された保存要件に沿って電子保存することになると考えられます。
加えて、上図(2)に記載されているように、仮に当該電子インボイス(電子取引の取引情報に係る電磁的記録)が、申告漏れ等に関係したデータだった場合、重加算税が課される恐れも発生することになるため、電子インボイスは、電子帳簿保存法の保存要件に対応しつつ、隠蔽、仮装等が起きないシステム運用が求められている、といえます。
では、不正を抑止し得るシステムには、どのような対応が求められるのでしょうか。ヒントは、改正前の電子帳簿保存法の規定内容にあります。
8.電子帳簿保存法の改正事項に応じたシステム化のポイント
電子帳簿保存法は、今回の改正で厳格な規定が大幅に緩和されました。ただし保存要件等が緩和されて不正等が発生してしまっては、電子帳簿保存法に対応する意味がありません。そのため「改正前後の内容を踏まえたシステム対応を検討する」ことは、電子帳簿保存法やインボイス制度への対応には欠かせない対応となってきます。
どのような対応観点が必要になってくるのか、スキャナ保存の緩和事項を例に、以下の3つの改正事項から求められるシステム対応のポイントを示します。
(1)事前承認制度の廃止に伴う第三者確認の必要性
改正前は、原則3か月前までに所管の税務署へ電子帳簿保存法への承認申請を実施し、承認が得られてから、電子帳簿保存法に沿ったシステム対応を実施してきました。
改正後は、所管の税務署の事前承認が不要になりました。そのため税務署の事前審査に代わって3か月程度前からの事前準備と、可能な限り第三者による実施内容の事前確認があるとよいでしょう。国税庁では、巻末に紹介する相談窓口も設けているので、電子化への対応に不安な点があれば、相談窓口も活用しましょう。
(2)タイムスタンプ要件の緩和に伴う本人認証機能と申請管理機能
改正前は、領収書等の証憑の原本の受領者が署名(自署)と、3営業日以内にタイムスタンプを付与することが必要でした。
改正後は、署名が不要となり、電子化後は原本の破棄も可能です。またタイムスタンプの付与期間も最長約2か月と概ね7営業日以内へと大幅に緩和されました。そのため本人の署名に代わるシステム機能によって、なりすましを防止した認証機能(二段階認証等)や、タイムスタンプ付与期間なども自動管理できる申請管理機能が必要となります。
(3)適正事務処理要件の廃止に伴うシステムチェック機能等の整備
改正前は、不正利用防止の目的で適性事務処理要件の要件として最低でも2名以上で相互牽制が機能する運用体制が求められていました。また定期的な実地検査と、不正等が発生した場合の再発防止策を定めた社内規程の整備も必要でした。
改正後は、こうした適性事務処理要件が廃止されました。2名以上の相互牽制体制を築けない場合は、人の眼に代わってシステムによる相互牽制機能が必要です。1人で電子化しても不正が発生しにくい不正防止機能や、定期的な実地監査に代わる申請チェック機能などを整備する必要があります。また万一、不正が発生した場合は、再発防止策を柔軟なシステム改修で対応できることも重要なシステム対応ポイントとなります。
9.電子帳簿保存法とインボイス制度へのシステム対応
インボイス制度については、最近テレビCMでも目にするようになり、それなりに周知されてきていると思いますが、電子帳簿保存法となると、途端に理解度は下がると思います。
更には、今回解説したようなインボイス制度と電子帳簿保存法の法制度を踏まえた対応となると、相当な専門性も必要になってきます。こうした背景も踏まえて、国税庁からはこの度、電子帳簿保存制度・特設サイトが開設されました。

出典:国税庁 電子帳簿保存制度・特設サイト
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm
この特設サイトで特に強調しているのは、電子取引データの義務化がなされた電子取引です。電子帳簿保存法の要件適合性に関する相談窓口も開設されているので、是非参考にして下さい。

出典:国税庁 電子帳簿保存制度・特設サイト
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm
電子取引における電子データの保存が義務化されたことで、電子取引で受領したPDFによる適格請求書(インボイス)は、改正された電子帳簿保存法の要件に沿った電子保存の義務が発生します。
一方で郵送等により紙(書面)で受け取った適格請求書(インボイス)を電子保存する際も、同様に電子帳簿保存法の保存要件に沿って保存しなければなりません。
更には、インボイス制度における適格請求書発行事業者の義務を順守し、受領した適格請求書(インボイス)と発行した適格請求書(インボイス)の控え(写し)は、紙であれ電子であれ7年間の保存義務が課されています。
現実的には紙(書面)の運用は、直ぐには無くならないので、多くの事業者は、紙の運用に加えて、電子データの管理を義務として運用することになります。そのため、これらのシステム対応が求められる運用には、経理業務に特化したITベンダとの一体的な取り組みが欠かせません。
私たちファーストアカウンティングは、経理業務に特化したソリューションベンダです。先進のAI-OCR技術や経理業務に求められるチェック機能や監視機能のほか、既存システムとの連携には欠かせないRPA等の活用実績も多数保有しています。インボイス制度と電子帳簿等保存制度の両方に対応する私たちの豊富な対応ノウハウは、貴社の請求・経理業務の効率化に寄与できることを確信しています。
インボイス制度の開始前に、私たちファーストアカウンティングのDX(デジタルトランスフォーメーション)ソリューションを、是非ご検討ください。
巻末資料1:スキャナ保存要件(令和4年1月以後にスキャナ保存を行う場合の要件)
| 書類の区分 | 重要書類 | 一般書類 |
| 資金や物の流れに直結・連動する書類 | 資金や物の流れに直結・連動しない書類 | |
| (例)契約書、納品書、請求書、領収書 など | (例)見積書、注文書、検収書 など |
| 入力期間の制限 | 【早期入力方式】国税関係書類に係る記録事項の入力をその受領等後、速やか(おおむね7営業日以内)に行うこと | |
| 【業務処理サイクル方式】国税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間(最長2か月以内)を経過した後、速やか(おおむね7営業日以内)に行うこと *国税関係書類の受領等から入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る | ||
| 【適時入力方式】適時に入力(注) | ||
| 一定水準以上の解像度及びカラー画像による読み取り | (1)解像度が 200dpi相当以上であること (2)赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ 256 階調以上(24 ビットカラー)であること | |
| (2)に関しては、白黒階調(いわゆるグレースケール)での読み取りも認められる。(注) | ||
| タイムスタンプの付与 | 入力期間内に、一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプ(電磁的記録が変更されていないことについて、保存期間を通じて確認することができ、課税期間中の任意の期間を指定し、一括して検証することができるものに限る)を、一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に付すこと ※ 入力期間内にその国税関係書類に係る記録事項を入力したことを確認できる場合には、このタイムスタンプの付与要件に代えることができる | |
| 読取情報の保存 | 読み取った際の解像度、階調及び当該国税関係書類の大きさに関する情報を保存すること ※ 国税関係書類の受領者等が読み取る場合で、当該国税関係書類の大きさがA4以下であるときは、大きさに関する情報の保存は不要 | |
| 大きさに関する情報の保存は不要(注) | ||
| ヴァージョン管理 | 国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができる電子計算機処理システム又は訂正又は削除を行うことができない電子計算機処理システムを使用すること | |
| 入力者等の情報の確認 | 国税関係書類に係る記録事項の入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認 できるようにしておくこと | |
| 帳簿との相互関連性の確保 | 国税関係書類に係る記録事項の入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認できるようにしておくこと | |
| 見読可能装置の備付け等 | (1) 14インチ(映像面の最大径が 35cm)以上のカラーディスプレイ及びカラープリンタ並びに操作説明書を備え付けること (2)電磁的記録について、次のイ~ニの状態で速やかに出力することができるようにすること | |
| イ 整然とした形式 ロ 当該国税関係書類と同程度に明瞭 ハ 拡大又は縮小して出力することが可能 ニ 4ポイントの大きさの文字を認識できる | 白黒階調(いわゆるグレースケール)による保存の場合、ディスプレイ及びプリンタはカラー対応である必要はない。(注) | |
| 電子計算機 処理システムの概要書等の備付け | 電子計算機処理システムの概要を記載した書類、そのシステムの開発に際して作成した書類、操作説明書、電子計算機処理並びに電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類を備え付けること | |
| 検索機能の確保 | 電磁的記録の記録事項について、次の要件による検索ができるようにすること (1) 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先での検索 (2) 日付又は金額に係る記録項目について範囲を指定しての検索 (3) 2以上の任意の記録項目を組み合わせての検索 ※ 税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができ るようにしている場合には、(2)及び(3)の要件は不要 | |
(注)一般書類のスキャナ保存を行う場合の要件です。また、そのスキャナ保存を行う国税関係書類に係る電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(これらの事務の責任者が定められているもの)の備付けを行う必要があります。
出典:国税庁 はじめませんか、書類のスキャナ保存
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_02.pdf
巻末資料2:電子帳簿保存法・インボイス制度のお問い合わせ先
国税庁Webサイトは情報量が非常に多く、問い合わせ先の検索に時間がかかるかもしれません。また電子帳簿保存法とインボイス制度では問い合わせ先が異なるので注意が必要です。
■電子帳簿保存法の要件適合性に関する相談窓口
本サイトに問い合わせ先の国税局等は直接リンクされていないので、以下の地図表示のサイト等から所轄の税務署、国税局を検索してください。

出典:国税庁 電子帳簿保存制度・要件適合性・事前相談窓口
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/10.htm
■税務署の所在地などを知りたい方(所轄の税務署、国税局の検索サイト)

出典:国税庁 税務署などの所在地を知りたい方
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/10.htm
■消費税の軽減税率制度及びインボイス制度に関して相談する(軽減・インボイスコールセンターのご案内)

出典:国税庁 国税に関するご相談について 軽減税率制度及びインボイス制度について相談する
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm
■軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)

出典:国税庁 軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/04-1.htm